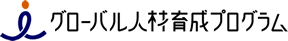本連載では、1年にわたって、人事・人材開発担当者が知っておきたい人材マネジメントに関するベーシックな理論や最新情報をピックアップしてきました。最終回は、連載を振り返りながら、グローバルHRに携わるみなさんを取り巻く急激な環境変化、それに伴う人材開発のあり方、人材開発部門の役割を整理します。
![]() <相談内容>
<相談内容>
4月に新設されたグローバル人材開発担当へ異動しました。わが社は、海外事業の急成長に伴い、グローバル人材育成が急務だそうですが、私は海外営業を担当していたので、人材開発分野の専門知識がほとんどありません。どのように仕事に取り組めばよいでしょうか?
(20代後半 男性 人事部 グローバル人材開発担当 F.M.)
【解説】
F.M.さんの会社に限らず、リーダー不足の解消に向け、多くの組織が人材マネジメントに取り組んでいます。2014年のコンファレンス・ボード(全米産業審議会)のグローバル調査では、CEOが最も重視する経営課題は、「顧客リレーション」「イノベーション」などを押さえ、「人的資源(HR)」が第1位。さらに、「人的資源」分野の課題に対する最重要施策は、「社員の教育訓練、能力開発」です[*1]。リーダーシップの実態に関するグローバル調査では、「自身の組織のリーダーシップの質が高い」と回答した人は、リーダー1万3千人の40%、人事専門職1,500人の25%に過ぎません。「3~5年後に事業を担う次世代リーダー人材の量・質の充実度が高い」と答えた人事専門職はわずか15%です。日本の結果は、リーダーシップの質、次世代リーダー人材の量・質の充実度、ともに調査対象国中、最低レベルだそうです[*2]。
現状打開に向け人材開発への取り組みの加速が求められますが、F.M.さんのように異動でたまたま人材開発を担当し、知識や経験が浅いため戸惑うという人は、日本企業では少なくありません。そこで今回は連載のまとめとして、グローバルHRを取り巻く環境変化、これからの人材開発のあり方を整理し、F.M.さんのような人材開発に携わる人に求められる意識・行動を考察していきます。
人材開発をめぐる三つの環境変化
まず、企業の人材開発に影響を与えているグローバルレベルの環境変化を捉えておきましょう。ここでは、「グローバル化の進展」「働く人の世代交代」「ICT(情報通信技術)の進化」を取り上げます。
(1)グローバル化の進展
近年、世界中の企業が地球規模の事業活動を目指し、グローバル事業展開を進めています。日本企業も人口減少や経済停滞による国内市場の縮小で、海外現地に根差したグローバル市場開拓に本格的に乗り出しました。同じ有望市場を狙う優れたグローバル企業がライバルとなり、人材の獲得や活用も地球規模の競争に入ります。優秀な人材は、国籍にかかわらず世界中の企業を舞台に活躍するため、彼らが魅力を感じて組織に留まる人材マネジメントの仕組みづくりが求められます。海外拠点では、「日本企業は横並びで登用のスピードが遅く、実力主義とは言い難い」と捉えられ、欧米企業に比べ相対的に現地人材に人気がないようです[*3]。そのため、グローバルでの活躍を目指す、上昇志向に溢れた優秀な人材の獲得や活用に向けた「日本的人事慣行」の見直しが課題となっています(詳しくはChapter3参照)。
グローバル化の進展は、ビジネス環境の変化のスピード、不確実さ、複雑さの度合いを高めます[*2]。急速な環境変化に合わせ、企業の事業構成や事業内容が変わると、組織のリーダーに求められる資質や能力といった人材の「質」が変わります。また、インド・中国のような急成長中の地域では、事業の急拡大に採用や人材育成が追い付かず、リーダーの「量」が不足してきます。前述のリーダーシップの実態調査によると、組織の重要な役職の54%は、社内では後任がすぐに見つからないそうです[*2]。質・量両面でのリーダー不足は、事業展開のボトルネックになりかねません。リーダー人材層の拡充は、競争の優劣につながる最重要課題の一つなのです(詳しくはChapter3、Chapter8参照)。
(2)働く人の世代交代
1990年代以来、劇的に発展を遂げたテクノロジーによって、人々の働き方が変わりました。インターネットのような通信手段が世界中の人々を大規模につなげ、グローバルな雇用や知財市場を生み出しています。人口構成の変化は、個人、家族、社会の価値観を大きく変えています。仕事では、金銭よりもやりがいを重んじる人が増え、キャリア移動は常識になり、働き方そのものが多様化しています[*4](詳しくはChapter1、Chapter11参照)。
今後組織の中核となる新たな世代(ミレニアル世代[*5])は、幼い頃からデジタル社会に親しみ、デジタルで他者と日常的に交流するソーシャルネットワーク文化で育ちました。彼らは職場を他者との協創、学習の場と捉え、組織が提供する集合研修や職場のOJTだけに頼らず、自分で必要性を見極めて自主的に学びます。それ以前の世代とは学習スタイルが異なるため、組織が決めた教材で一律に学ぶ既存の教育研修は通用しづらくなっています。
彼らが組織へ参入することで、企業の組織学習のあり方が変わってきています。これまでの主流は、組織が過去に蓄積した知識・スキルを、講師が未熟な学習者に教え込むコンテンツ中心の学校教育式でした。最近では「学習者中心主義」といって、学習者を経験を積んだ主役と捉え、周囲の環境、人との交流、仕事の経験を通じた、彼らの主体的な学びを組織が支援する傾向が高まっています。環境が加速度的に変化するため、過去に蓄積された知識・スキルは5年も経つと陳腐化し、実務で活用しづらくなります。そのため、学ぶ目的、内容、学び方は、変化の中から学習ニーズを感じ取り自ら学ぶ学習者に、委ねられてきているのです(詳しくはChapter7参照)。
(3) ICT(情報通信技術)の進化
「学習者中心主義」の追い風となっているのが、ICTの進化による学びと教えのオープン化です。教材のデジタル化、ウェブ上での公開によって、時間、地域、組織、費用といった制約が減り、企業の教育研修に頼らずとも、意欲の高い学習者が自身の興味やキャリア形成意識に基づいて自由に学べるようになりました。例えば、マサチューセッツ工科大学から始まり、米国の大学を中心に広がった大規模オンライン公開講座(MOOCs)では、世界トップクラスの大学が提供する最先端の講義に無料で参加できます。企業内では、スマートフォンやタブレット端末などのモバイル機器を使った、時間や場所を問わない学習(モバイルラーニング)も導入され続けています。社内にモバイル機器用の教材を持つ企業は、2010年にはたった3%でしたが、2015年のグローバル調査では34%に増えています[*6]。
さらにウェブ上には、ソーシャルメディアを使った自由でオープンな学習(ソーシャルラーニング)の場が次々と生まれています。ブログ、ツイッター、フェイスブックのような、誰もが参加できるソーシャルメディアは、学習者同士が知識、情報、学習のコツを共有する協働学習の場となっています。例えば、ソフトウェア企業のSAPのブログを使った学習コミュニティには、社内外のエンジニア200万人が参加しています[*7]。参加者は各々の学習ニーズに沿って知識や経験を交換し、投稿した質問や意見には平均17分で最初のレスポンスが来るそうです。ここには、早く回答すれば評価ポイントがもらえ、ポイントが高い人は希望のプロジェクトに入りやすくなる学習管理の仕組みもあります。そのため、参加者同士で教え合う協働学習への意欲がさらに促される好循環が生まれているのです(詳しくはChapter10参照)。
人材開発担当者の四つの役割
「グローバル化の進展」「働く人の世代交代」「ICT(情報通信技術)の進化」により、企業の組織学習のあり方が変化しています。では、人材開発部門の役割、担当者に求められる意識・行動はどのように変わるのでしょうか。下図は、人事の研究で著名なミシガン大学のウルリッチ教授が長年提唱している人事の役割フレームワーク[*8]の4分類にならい、で、人材開発部門のあり方を筆者が定義したものです。この分類を参考に、人材開発部門の役割、担当者に求められる意識・行動を整理していきましょう。
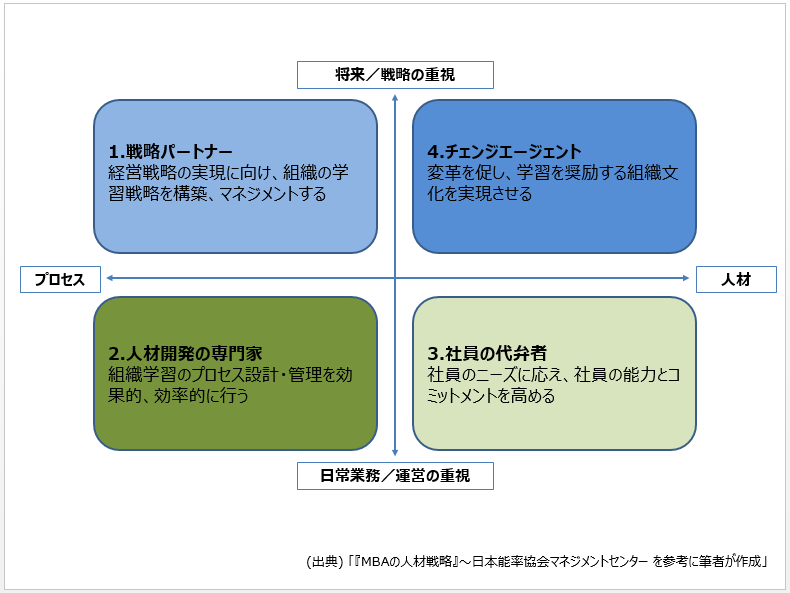
人材開発活動のゴールは事業の成果を上げること
「戦略パートナー」としての人材開発部門の役割は、グローバル事業展開のようなビジネスの戦略実現に向け、人材開発を通じて経営を支援することです。株主から「利益目標必達」「継続的な成長」を厳しく求められるグローバル企業の人材開発部門は、事業部門の主要ポジションを担える人材の獲得、育成、定着を支援する「事業部門のパートナー」を自認しています。例えば、優れた人材開発部門は、組織学習のゴールに事業の成果指標を組み込み、結果を検証して次の学習活動に生かす、というサイクルを回します。組織学習の成果に関する調査では、「自社の事業のゴールと組織学習のゴールが連動している」と考える企業の割合は、高業績企業では72%、低業績企業では53%でした。「自社の人材開発部門は効果を上げている」と考える企業は、高業績企業では55%に上りますが、低業績企業では28%に留まっています[*9]。人材開発部門は、事業のゴールと組織学習のゴールを連動させることで、業績向上に貢献し、効果性を高めるのです。
事業成果に貢献するには、事業部門の責任者と協力し、事業部門が重んじる課題に焦点を定め、事業部門の人材のパフォーマンス発揮状況を常に把握することが欠かせません。そのため、人材開発部門のメンバーには、自社の事業に関する知見を高めることが求められます。前述の調査によると、「人材開発部門は自社の事業に関する知見が高い」と答えた企業の割合は、高業績企業では74%、低業績企業では57%でした。自社事業への知見の高さは、企業業績や人材開発部門の効果性と正の相関があることも分かっています。(詳しくはChapter6を参照)。
専門知識を活かして組織の学習プロセスを活性化する
次に、「人材開発の専門家」としての人材開発部門の役割について考えます。日本企業では長期雇用が前提のため、社員に複数の部署を経験させ、時間をかけて本部主導で社員を育成、選抜、評価する傾向があります。そのため人材開発部門の主要業務は、階層別研修に代表される全社共通の学習プログラムを作り込み、コンテンツや集合研修を管理運営することでした。しかし社員の学びの自立が高まれば、従来のように組織が社員の学習内容をすべてコントロールすることは難しくなるでしょう。そうなると人材開発部門の役割は、個々の教材作成や研修運営よりも、組織成果の達成に向けた組織の学習環境の整備、学習プロセスの設計、活性化に力点が移ります。具体的には、組織目標達成に向けた効果的な学習プロセスや社員の学習目標の見極め、学習目標到達に向けた教材の選択・集積、インフォーマル学習の場づくり、到達度合の把握などの職務になるでしょう。
人材開発部門のメンバーには、効果的な施策の構築、推進に向け、専門的な知見・スキルを持った人材開発のプロフェッショナルであることが求められます。広く普及している学習理論を学び、経験学習、相互学習、ソーシャルラーニング、インフォーマルラーニングといった学習者中心の学習法への知見を高めましょう。また、今後組織の中心となるデジタル世代の学習ニーズや学習スタイルを知り、モバイルラーニングや社員の学習コミュニティを支える学習テクノロジーに親しむことも必要でしょう。(詳しくはChapter7、Chapter10を参照)
働きがいのある組織をつくり、社員のやる気を高める
「社員の代弁者」としての人材開発部門の役割は、社員のエンゲージメント向上を引き出して、パフォーマンス発揮に結び付けることです。2011年のグローバル対象の調査によると、日本企業の社員のエンゲージメントは世界最低水準だそうです[*10]。エンゲージメントの低さは、仕事の生産性の低さにつながります。今後ますます少子高齢化が進み、少ない労働力で高い業績を上げることを求められる日本企業にとって、エンゲージメント向上は重要な課題です。
ワクワクする挑戦しがいのある仕事を尊敬し合える仲間と一緒にできて、常に成長実感が持てる職場では、社員はよりエンゲージメントを高め、優れたパフォーマンスを発揮します。そのため、人材開発部門のメンバーには、社員のキャリア開発、能力開発、組織開発を通じて、そのような"働きがいのある組織づくり"を支援することが求められます。具体的に課題があると判断した現場・個人に対しては、マネジャー任せにするのではなく、原因を探り、速やかに課題解決を支援することも大切でしょう。例えば、チームのモチベーション低下がゴール達成の妨げになっている組織には、オフサイトミーティングやリーダーのコーチングを実施する。経験の浅い社員に対し、キャリアや能力開発の相談に直接乗る「メンター」となる。このように、具体的に社員のパフォーマンス改善、個人の成長、能力開発につながる支援を、現場に踏み込んで提案、実施することが望ましいのです。それには、キャリア開発、組織開発の知識とともに、ファシリテーションやコーチングの手法を使いこなすことも求められるでしょう。(詳しくはChapter1、Chapter4、Chapter9、Chapter11を参照)
学習を奨励する組織文化をつくる
人材開発部門の役割の四つ目は、「組織文化のチェンジエージェント」です。人材開発を効果的に進めるために最も重要な要素は組織文化です。時間、費用、人を投入し学習環境を整えても、組織文化が学習を奨励していなければ、社員も仕組みも効果的に動きません。自発的な学習が公に奨励されていても、「研修は時間と労力のムダ」「学習する暇があったら仕事に打ち込め」といった意識が組織に暗に根付いていれば、社員は学習に消極的になるでしょう。したがって、人材開発部門のメンバーには、学習を奨励する組織文化の構築・促進に向けた課題を発見し、事業部門のリーダーや社員、経営陣を巻き込んで、課題解決に取り組むことが求められます。
例えばGEでは、非常に多忙な現役リーダーたちが貴重な時間を割いて、リーダー候補者との対話やアクションラーニングのコーチ役を務めます。彼らは自身の経験から、リーダー候補者の育成には現役リーダーの薫陶が不可欠なことを知っています。次のリーダー育成は現役リーダーの重要な役割だという文化が、組織に根付いているのです[*11]。
グーグルの「20%ルール」(開発者が、就業時間の20%を自身の本業以外の製品・アイデアの創造、改良プロジェクトに充てる仕組み)は、開発者の創造性を高める学習環境の一つです。開発者は就業時間を使って新しいアイデアを探究し、面白いアイデアは他者を巻き込み実現することを奨励されます。グーグル・ニュース、Gmailなどは、この仕組みから生まれたそうです。グーグルではマネジャーに、通常の「スパン・オブ・コントロール(一人の上司が管理できる部下の数)」を越えた人数の部下を意図的につけるそうです。部下の数を増やし、上司が部下の仕事を必要以上にコントロールできないようにして、部下の創造性を促すのです[*12]。同社では、そこまで徹底して社員の創造性発揮を重んじる組織文化が守られています。この組織文化があって初めて、「20%ルール」のような社員の創造性を高める学習環境が効果的に機能するのです。
人材開発部門へ異動したばかりのF.M.さんは、人材開発の仕事の広さと専門性に驚いているかもしれません。実は海外の企業では、大学院などの専門教育機関で人材開発・組織開発を体系的、専門的に学んだ人が、人材開発担当に就くのが一般的です。そのため、組織の人材開発は、専門性が高く、実績のある方法論・手法で構築、実行されます。一方、多くの日本企業では、人材開発部門にそれらの専門性を持つ人を採用、配置することはまだ少ないようです。そのため、組織固有の考え方、経験を拠り所にした"自社流"のやり方で奮闘している人も多いと聞きます。人材開発・組織開発の体系的な知識・方法論に馴染みが薄い人は、自らの仕事を企業成長に向けた戦略的、体系的な取り組みと捉えず、個別研修の企画・運営に限定しがちです。人材開発がどれほど組織成果へ貢献するのかを考えれば、大きな差がついていると言えるでしょう。中国、インド、東南アジアなど日本以外の国は、グローバル企業の人材育成のあり方をスタンダードとして取り入れ、成果を上げています。日本企業も後れを取るわけにはいきません。世界中で人材開発のプロフェッショナルたちが共通言語とする考え方・方法論を学んで活かす時期に来ているのです。
これまで、12回にわたりご愛読くださいましてありがとうございました。この連載で取り上げたトピックが、読者の皆さんの仕事に少しでも役に立つとうれしく思います。皆さんが人事・人材開発のプロフェッショナルとして、さらに知識・スキルを磨き、"一歩一歩(Step by Step)"前進を続けることを願ってやみません。
リンクは記事掲載当時のものとなります。
*1:
Mitchell, C.,Ray,R.L.,&vanArk,B., The Conference Board CEO Challenge 2014: Peopleand Performance, New York, The Conference Board, www.conference-board.org![]()
*2:
DDI「Global Leadership Forecast 2014-2015」2014年
*3:
日本経済団体連合会「アジアにおいて求められる人材マネジメント」2008年
*4:
『ワーク・シフト』リンダ・グラットン著、プレジデント社、2012年
*5:
1980年代から2000年にかけて生まれた世代。米国のミレニアル世代は、8千万人とされ、2025年までに全米の就労人口の75%を占めると言われる。
*6:
「The Mobile Landscape 2015: Building Toward Anytime, Anywhere Learning」ATD Research,2015
*7:
SAP社の学習コミュニティ SAP Community Networkは以下のサイトを参照
http://scn.sap.com/welcome?original_fqdn=www.scn.sap.com![]()
*8:
『MBAの人材戦略』デイビット ウルリッチ著、1997年、日本能率協会マネジメントセンター
*9:
「Developing Results:Aligning Learning's Goals and Outcomes with Business Performance Measures」Whitepaper Volume3/No.5、ASTD Research、2012年
*10:
「Engaging Level in Global Decline」A Kenexa Research Institute WorkTrends report、2011年
*11:
『戦略人事のビジョン』八木洋介、金井壽宏著、光文社新書、2012年
*12:
『How Google Works』エリック・シュミット、ジョナサン・ローゼンバーグ他著、日本経済出版社、2014年