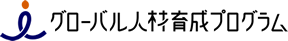Global Frontline~グローバルな舞台でチャレンジする人たち~


私にも、世界を少しでもよりよくするためにできることが、きっとある
プロフィール
伊藤菜々美(いとう・ななみ)
小学5年生のとき、南太平洋の国・トンガ王国を訪れ、世界の文化の違いに興味を持つが、数週間後に起きたNYの同時多発テロにショックを受け、子どもの自分に何ができるのか分からず葛藤するように。高校生になり、学校の英語の教科書をきっかけに児童労働問題や子どもにもできるアクションに関心を抱き、国際協力に関わり始める。大学時代は演劇を通じた啓発活動や、カナダの国際NGO本部でインターンを1年経験。一般企業での勤務を経て、2016年フリー・ザ・チルドレン・ジャパン入職。現在、年間約1万人の学生に対し講演会・ワークショップを実施、またチェンジメーカーの子どもたちのためのライブイベント「Change Makers Fes」のプロジェクトマネージャーを担当。これまでに32カ国を訪問。他にも「世界のワクワクとモヤモヤの両方を知って、世界をもっと身近に!」をテーマに活動中。
世界は多様性に富んでいると気付かされたトンガ滞在

2001年当時のトンガ王国の王様を訪問
私が世界の広さを初めて実感したのは、小学5年生のときに訪れたトンガでの体験がきっかけでした。小学1年生の時からそろばん教室に通っていたのですが、数年に1度、夏休みの期間に複数の教室の生徒たちで海外に渡り、そろばんを通じて交流をする「国際珠算親善使節団」の活動が国際珠算普及基金によって行われていました。私はその一員として、オーストラリア、トンガ、ニュージーランドの3カ国を訪れることになったのです。その頃の私が抱いていた海外の国々のイメージといえば、ニューヨークの自由の女神やオーストラリアのオペラハウスのような象徴的な建物、あるいは歴史ある建物が並ぶヨーロッパの街並み、もしくは家族旅行で訪れたタイのプーケットのようなリゾート地といった、とても限られたものでした。ですので、トンガがどんな国なのか、想像すらできない状態でした。
まず驚いたのは、歓迎イベントで出迎えてくれた現地の人々の服装です。裸足に、樹皮や葉っぱで編んだものをエプロンのようにズボンの上から腰に巻いた人がたくさんいましたし、小さな子どもたちも葉や藁でつくられた衣装を身にまとい伝統的なダンスを踊ってくれました。タヒチアンダンスのようなものだったと思うのですが、初めて生でそうした衣装で踊る様子を見て、とにかく衝撃を受けました。そして、その場で振る舞われたご馳走が豚の丸焼き。切り分ける前の豚の姿をそのまま留めた状態で、草の上に載せられて運ばれてきたのです。初めて目にしたこともあって、これにもびっくりしました。
言葉の違いも驚きの一つでした。トンガは英語も公用語ですが、日常生活では現地語であるトンガ語が話されることが多いです。英語以外の言語にほとんど触れたことがなかった私にとって、トンガ語の響きはとても新鮮に聞こえました。よほど印象的だったのか、そのときに覚えた現地の歌のフレーズを今でも口ずさむことができます。未だに意味は分からないのですが(笑)。
このようにトンガは日本とは文化も風習も違えば、街並みも違う。そこで暮らす人々の見た目も違えば、話す言葉も、生活スタイルも違う。世界には、もっと違った人々や文化が存在するのではないか。そう考えるだけでワクワク感が高まってきて、もっとたくさんの違いを知りたい、見たい、触れたいという思いが強くなっていきました。それを実現するには、外国語、特に英語はできたほうがいいだろうということで、帰国後、親に頼んで英会話教室に通わせてもらうことになりました。
「モヤモヤ」の先に見つけた自分にできること
トンガで広い世界への好奇心が芽生えて間もなく、その気持ちが萎縮してしまう出来事が起こります。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件です。黒煙を噴き上げるワールドトレードセンターの様子をテレビのニュース番組で目にしたとき、世界にはこんな恐いことが起こる場所もあるんだと絶望のようなものを感じました。もう海外には行きたくないとまではならなかったものの、安心して日々の生活を送れない人々がいることに改めて気付かされました。そんな怖い思いをしている人がいる状況を変えることができればいいのですが、私にはその力はない。そこから、葛藤というと大げさかもしれませんが、どことなくモヤモヤした思いを抱くようになったのです。
こうして以前のようなワクワク感だけで海外に目を向けることができなくなってしまった私ですが、高校2年生のときに再び心のあり方が大きく変わる出会いを経験します。それは英語の教科書に載っていた、一人のカナダ人少年の物語でした。
彼は12歳のとき、パキスタンでの児童労働の問題を知り、友人たちを誘ってボランティア団体を設立します。そして周囲の大人たちをはじめ多くの人を巻き込み、集めた寄付金で途上国に学校をつくるなどの活動を行っているということでした。少年の名は、クレイグ・キールバーガー。彼が設立した団体が、フリー・ザ・チルドレンです。

目の前がパッと明るくなった気がしました。12歳の少年でも、世界にポジティブな変化を生み出している。それなら、今の私にだってできることがあるのではないか。そう思うことができたのです。
調べてみたところ、フリー・ザ・チルドレン・ジャパン(FTCJ)という日本で活動をしている団体があり、有志のグループでそこに支部として加盟することができると分かりました。学校で支部をつくろう。そう思って、名簿を持って各教室を回ったのですが、賛同してくれる人がただの一人も現れませんでした。同じ学校の同級生なら、授業でフリー・ザ・チルドレンのことを知り、私と同じ思いを抱いた人もいるはず。そう期待していたのですが……。
今思い返すと、一人でまずは何かやってみる、ということもできたと思うのですが、当時は「仲間が見つからなかったからできないんだ……」と思ってしまいました。そこで、まずは世界の問題などを学ぼうと考え、大学進学に向けて頭を切り替え、そちらに集中することにしました。
ただ、このときに抱いた「自分にも世界をよりよくするためにできることがある」という思いは消えることはなく、大学進学後には自身でボランティア団体を立ち上げ、チャリティーイベントを開催するなどの活動に励みました。すると、「偽善じゃないの?」「自己満足でやっているだけでしょ?」といった声がチラホラと漏れ聞こえてきます。当時の私にはそれに対して堂々と反論できる言葉を持っておらず、またしてもモヤモヤした気持ちが募るようになってしまったのです。そうした私の心理状態の影響もあってか、団体の活動も徐々に停滞するようになってしまいました。
インドで出会った女性との交流で迷いを振り切る
このままではいけない。原点に立ち返って、なぜ自分はボランティア活動を行うのか。それを改めてじっくりと考える必要がある。そのためにも、支援を受ける立場の人たちの思いを知りたくなりました。実は、私は大学入学間もない頃からイベントの手伝いなどでFTCJとの関わりを深めていました。その縁で、夏休みにFTCJがインドへのスタディツアーを開催することを知り、それに参加することにしたのです。

2010年大学2年生の時インドスタディツアーに参加、農村で出会った16歳のお母さん
訪問したのは、カースト制度で低い階層と位置付けられ、差別を受けるようになった、山奥にある少数民族の村でした。行く前は、きっととても悲惨な生活を送っているのだろうと想像していたのですが、実際に目にした光景はずいぶん違ったものでした。
確かに、すごく貧しい境遇ではあるのですが、とにかく子どもたちが明るく元気。それを見守る親御さんたちもニコニコ笑っていて、意外なほど笑顔が多いのです。でも、それはあくまでも表面的なものに過ぎないことは話を聞いて分かりました。特に印象に残ったのが、16歳の女の子です。その年齢ですでに母親になっている彼女が「こんな人生、大嫌い」と吐き捨てるようにつぶやいた表情が、今でも脳裏から離れません。そこには、大嫌いなのに、好きになれるように変えることもできない絶望感がありありと浮かんでいました。まだ子どもといっていいくらいの年齢なのに、もう人生を諦めてしまっているのです。私は胸が締め付けられるような思いがするとともに、彼女のような人たちの力になれる仕事をしたいという気持ちがフツフツと沸き上がってくるのを感じました。
進むべき道がはっきりすれば、後は行動あるのみです。日本に帰国後に私がまず始めたのは、インドで知った児童婚や児童労働などの実態を演劇で伝える活動です。なぜ演劇かというと、私は小学生の頃から演劇が好きで、舞台やミュージカルの経験があったことと、そのほうがメッセージが伝わりやすいと思ったからです。「劇団員」はFTCJの活動で知り合った子どもや学生たちで、私は脚本と演出、ときには出演の3役を担いました。参加者も私も、演じることで実際の子どもたちの気持ちを考えることができましたし、観てくれた人から胸が苦しくなった、涙した、何かできることはないか、と声をかけてもらうことも多くあり、意味ある活動だったと思います。
本気で頑張れば、応援してくれる人が現れる
学生時代の印象深い経験といえば、大学4年次に1年間休学して取り組んだカナダでのインターンシップも外せません。実務経験を積みながら英語も勉強したいと思い、トロントにあるフリー・ザ・チルドレンのオフィスにその旨をメールで伝えました。ところが、面接の日程を調整している途中で音信不通になってしまったのです。
FTCJで大学生メンバーとして活動はしていましたが、カナダと日本は組織としてはそれぞれ独立しています。採用に関して、カナダオフィスから特別な配慮をしてもらえるわけではありませんでした。就労希望者が多い人気の組織でもありましたし、カナダ在住ではない私のことは、後回しにされてしまったのかもしれません。
とはいえ、その時点で私はすでにカナダに行く気満々で、休学手続きも済ませていました。このまま連絡がつくのを待ち続けていても時間がもったいないので、思い切ってカナダに渡って直談判することを決意。そうしてトロントのオフィスを訪れたところ、私とメールのやりとりをしていた人に会うことができました。ところが、返事は「今はインターンの募集はしていないので、面接もできない」というものでした。
少なくとも面接はしてもらえるだろうと期待していたので、そのチャンスすら得られず目の前が真っ暗になりました。呆然としながらふらつく足取りでホームステイ先の家までどうにか帰り着き、玄関をくぐった瞬間、涙がボロボロとあふれ出して止まりませんでした。それを見たホストファミリーのお父さん、お母さんが驚いて駆け寄ってきます。私が泣きじゃくりながら事情を話すと、彼らはその場でフリー・ザ・チルドレンのオフィスに電話をかけました。そして、「遠い日本からわざわざやってきたのだから、その熱意を汲んで、せめて話だけでも聞いてあげてほしい」などと言って、先方を説得してくれたのです。その結果、面接の時間を設けてもらえることになったのです。
ようやくの思いでつかんだチャンスということで、面接では思いの丈を目いっぱい伝えました。フリー・ザ・チルドレンを知ったきっかけから、それによって自身に生じた変化、ここに至るまでの歩みなどを時間の許す限り話しました。するとなんと、無償でよければという条件付きではあるものの、インターンとして採用してもらえることになったのです。この一連の経験で学んだのは、本気で頑張っていれば、誰かが必ず応援してくれる。そして、それが更なる意欲を引き出してくれるということです。その思いは、今も私の心の真ん中で生き続けています。

2012年FTCカナダのオフィスにて
インターンでは、主に寄付をしてくれた人たちとのコミュニケーションを担当しました。礼状を送ったり、寄付の問い合わせの対応をしたりといった業務です。そこで感じたのは、カナダには寄付が文化として根付いているということです。寄付の件数自体もさることながら、驚いたのは、子どもからの寄付がとても多いこと。子どもの頃から習慣のように寄付をしているから、大人になっても継続し、自分の子どもにもその意義を伝えていくという、よい流れができているのでしょう。社会問題に関心が深い人が多いのも、そういった背景が影響しているのかもしれません。
カナダでの約1年間のインターンを終え、大学を卒業した後は社会経験を積むためにIT企業で2年間勤務したのち、FTCJに加わりました。
FTCJでは、主に出前授業に従事しています。小中高校、大学などを回っては、世界各国の児童労働や貧困などの問題の現状を知ってもらうとともに、たとえ子どもであっても自らアクションを起こすことで社会にポジティブな変化をもたらすことができるというメッセージを伝えています。また、新たなイベントとして「Change Makers Fes」を立ち上げました。これは社会問題に対して何らかのアクション(ソーシャル・アクション)を実践した25歳以下の若者を対象にしたイベントです。
ソーシャル・アクションを一人でやり続けるのはけっこうしんどいものです。世の中には、自分と同じ世代でさまざまなソーシャル・アクションを行っている人が大勢いると知って勇気づけられたり、仲間になってくれる人と出会ったりできる場があればと思ったのが発案のきっかけです。当初は2020年に開催の予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響で中止を余儀なくされ、21、22年もオンラインのみでの開催でしたが、23年は東京ドームシティホールを会場に、オンラインも合わせて1,500人に参加いただき、開催することができました。評判もとてもよかったので、今後も継続していきたいと思っています。
これからも、こうした活動を通じて社会問題への気付きやソーシャル・アクションの輪を少しずつでも広げていきたいですね。そうすることが、必要としている人に必要な支援がしっかり届く世界に繋がっていくと信じています。

――伊藤さんが大切にしていること
思いをきちんと言葉で伝えることです。カナダでのインターン時代、同じホームステイ先にベネズエラ人の留学生が滞在していました。彼女の紹介で南米人のコミュニティーとも交流するようになったのですが、ふだん英語漬けの生活をしている反動なのか、コミュニティー内では皆、スペイン語で会話するのです。ある日、私は居心地の悪さに耐えかねて、「英語で話してくれないと分からないよ」と言いました。反感を持たれるかなとも思ったのですが、意外にすんなり受け入れてくれ、私がいるときは英語で会話してくれるようになりました。親睦もより深まり、今では彼女がアメリカで結婚式を挙げたときには、招待されるほどの関係です。
インタビュー動画
記事の感想やご意見をお送りください
抽選で毎月3名様にAmazonギフトカード1000円分をプレゼントします
キャンペーン主催:(一財)国際ビジネスコミュニケーション協会
AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。