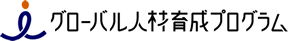Leader's Voice


身近な物事を世界とつなげて考え行動することで広がる世界
プロフィール
根本 かおる(ねもと・かおる)
1963年兵庫県生まれ。1986年、東京大学法学部を卒業後、テレビ朝日にアナウンサーとして入社。3年後に同局初の政治担当の女性記者として報道局政経部記者に異動。1994年、休職して米国コロンビア大学大学院に留学し、国際関係論修士号を取得。1996年から2011年末までUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)にて、アジア、アフリカなどで難民支援活動に従事。ジュネーブ本部では政策立案、民間部門からの活動資金調達のコーディネートを担当。WFP(国連世界食糧計画)広報官、国連UNHCR協会事務局長も歴任。フリージャーナリストを経て2013年8月より現職。
専門性を身につけるためにアメリカの大学院に留学

テレビ朝日に入社後、アメリカの経済や社会について専門性を身につけたい、英語をもっとブラッシュアップしたいと、コロンビア大学大学院への留学を決意したと語る根本さん。
私が生まれ育った神戸は、古くから多くの外国の方が暮らし、外に開かれた文化が根づいた街でした。そのせいか、「世界」というものが日常のなかにあったような気がします。当時、『兼高かおる世界の旅』という紀行番組が放送されていて、週末にその番組を見るのをとても楽しみにしていたことを覚えています。いつか私も世界を訪ね歩くことができたらいいな、と。
テレビ朝日に入社したのが1986年。ちょうど男女雇用機会均等法が施行された年で、就職活動をしていたのは施行前ですから、企業の女性総合職に対する姿勢はまだら模様といった状況でした。民放キー局の場合、報道や制作で女性が採用される会社は1社のみ。テレビ朝日はアナウンサー職に限られていました。
いざアナウンサーとして入社するも、関西弁が強くて「アナウンサーに向かないのでは」と思い、異動希望を出して政経部記者へ。テレビ朝日では女性初の政治担当記者の道を歩むことになりました。
私が担当したのは、日米自動車協議に代表されるような日米貿易摩擦の問題。アメリカの経済や社会について専門的に学んだことがないにもかかわらず、当時は得意顔で解説をしていたわけです。そんな自分が不甲斐ないと思ったのが、転機のきっかけでした。冷戦が終わって世界唯一の超大国となったアメリカで暮らし、専門性を身につけ、英語ももっとブラッシュアップしたい──いつしかそんな夢を描くようになったのです。しかし、そのころ、会社には留学の制度がありませんでしたから、幹部に直談判して制度をつくってもらうしかありません。幸い、私の願いを聞き入れていただき、ニューヨークのコロンビア大学大学院への留学を果たしました。
ニューヨークという場が生み出すダイナミックな学び
留学先をニューヨークに決めたのは、当時はメディアで仕事を続けていくことを念頭に置いていましたので、世界のメディアハブであること、また、国連本部があり、文字どおり国際政治の中心であることが大きな理由でした。
実際に、国連本部の幹部を含め、職員が講義に訪れることが頻繁にありました。大教室の授業もあれば、ゼミナール形式で議論をする機会もあって、国連が身近なものとして感じられるようになりました。また、テレビで議論されているような国際的な紛争の話がすぐに授業でも取り上げられ、議論の対象になる。まさに、実学です。学問と現実の世界がつながる、非常にダイナミックな体験でした。
クラスメートも多様性に溢れ、アパルトヘイトの闘士だった人や、天安門事件にかかわった人、国連のPKOで活動した実績のある人もいました。授業は、彼らとの議論が中心。自分はどう考えるのか、アクターとしてかかわっていける学びとでも言ったらよいのでしょうか。これまで、一方的に先生の話を聞くばかりの教育を受けてきた私にとっては、こうした学びのあり方に触れられたことは、何より得がたい経験だったと思っています。
大学院では国際人権法、なかでも国際難民法を専攻していました。時は1990年代半ば。UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)のトップは緒方貞子さん。私に国際法を教えてくださった先生は、難民条約の起草にかかわった方でした。こうした刺激溢れる環境に身を置くうちに、私の関心は難民支援の仕事へと傾いていったのです。
生き抜く姿勢を教えてくれた難民の人々

初めて支援の現場に携わった、UNHCRネパール事務所のインターン時代、ブータン難民の人々と。
初めて支援の現場に携わったのは、UNHCRネパール事務所でのインターンシップ。ネパールの難民キャンプでの支援活動を統括する事務所でした。そこで国連機関の活動を等身大のものとして見ることができ、自分にもできるのではないかと思いはじめました。日本の外務省が若手邦人を国連機関に派遣するJPO派遣制度の存在を知り、まだ在学中でしたが、試験に挑戦したのです。そして合格し、大学院を修了したのちは、マスコミの世界には戻らずに、国連機関でのキャリアをスタートさせる決心をしました。
最初の派遣先はUNHCRのトルコ事務所で、難民認定審査の仕事に携わりました。異文化の国で仕事をするにあたり、好奇心をもつことや、ダイバーシティを楽しみと捉える姿勢のようなものが原動力になりましたが、それに加えて、難民の方々の存在も非常に大きかったと思います。彼らは援助対象であると同時に、生きることについて教えてくれる「人生の師」でもありました。家族も財産も、何もかも奪われて逃げてきた人達は、とてつもない喪失感を抱えているはずなのに、それでも折り合いをつけて前に進んでいく。生き抜くということを、身をもって見せてくれていた。自分は、彼らから学ばせてもらっているのだと感じました。

ネパールのブータン難民キャンプにて、UNHCR現地事務所の所長として女性に対する暴力を廃絶する行進に参加。
一緒に働くチームのメンバーも多様性に富んでいて、そこには「当たり前」という概念は存在しません。日本独特の「阿吽の呼吸」「言わずもがな」などはありませんから、みんなできちんと共通のゴールを共有する必要があります。日本人にありがちですが、自己規制をして発言を控えていたのでは仕事にならないので、そのあたりはずいぶん鍛えられたという実感があります。
その後、インターンシップから10年近くの時を経て、再びUNHCRネパール事務所に、所長として赴任することになりました。当時ネパールでは内戦が繰り広げられていて、難民だけでなく職員の安全も確保しながら仕事をしなければいけない状況でした。めまぐるしく変わる安全状況を把握し、難民のため、チームのためを考えて先を読みながら進めていく。24時間緊張が伴う仕事でしたし、いろいろな意味で自分が試される局面が多かったです。
記事の感想やご意見をお送りください
抽選で毎月3名様にAmazonギフトカード1000円分をプレゼントします
キャンペーン主催:(一財)国際ビジネスコミュニケーション協会
AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
- 1
- 2