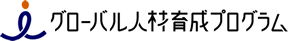Leader's Voice


スポーツと世界が私に教えてくれたこと
プロフィール
為末 大(ためすえ・だい)
1978年広島県生まれ。中学時代より陸上選手として目覚ましい活躍を見せる。男子100Mから400Mを経て400Mハードルに転向。スプリント種目の世界大会では、日本人として初めてメダルを獲得し、オリンピックはシドニー、アテネ、北京の3大会に出場。引退後、株式会社Deportare Partnersを創業。一般社団法人アスリートソサエティの代表理事、新豊洲Brilliaランニングスタジアム館長、国連ユニタール(国連訓練調査研究所)親善大使。『走る哲学』(扶桑社)、『諦める力』(プレジデント社)、『Winning Alone 自己理解のパフォーマンス論』(プレジデント社)、『為末メソッド 自分をコントロールする100の技術』(日本図書センター)など著書多数。
日本を飛び出したら、「世界」の概念がひっくり返った
私はこれまでの人生のうち、前半は陸上競技のアスリートとして、その後はスポーツ関連ビジネスの世界で活動してきました。その間、転機や決断の時は数知れずありましたが、人生の大きな節目となるようなターニングポイントは、2度経験しています。
一つ目のターニングポイントは、2000年のシドニーオリンピックの後にやってきました。人生初の五輪で、私は男子400Mハードルに出場したのですが、この時は予選で転倒。準決勝進出を逃す結果に終わりました。しかしオリンピックに出たことで、世界と競うなら、もっと世界を知らなければと、強く思うようになったのは大きな収穫でした。
翌年、私は単身ヨーロッパに渡り、各地を転戦する生活を始めました。あの時代の陸上競技はまだアマチュアリズムが強くて、選手が単独で海外の試合に参加することには、反対の声も結構あったのです。それにもかかわらず、思い切って日本を飛び出そうと決めた瞬間、一気にいろいろな殻が破れた気がしました。
日本を出てまず衝撃を受けたのは、自分の中にあった「世界」の概念が、ひっくり返ってしまったことです。私が抱いていたのは、日本の外に「世界」があって、自分は日本からそこへ乗り出して行くというイメージでした。私は「世界」という素晴らしい場で、自分がまだ知らない、グローバルスタンダードと呼ぶべき価値観を学ぶはずだったのです。
ところが現実の「世界」は、まるで想像とは違っていました。グローバルスタンダードどころか、てんでばらばらな背景や主張を持つ人たちがひしめく、カオスそのものだったのです。その中で揉まれながら、日本も自分自身も、最初からそのカオスの一部、世界の一員なのだという当たり前のことに、私はようやく気づいていったのです。それが23歳頃のことでした。

陸上選手として世界各地を転戦する決断をしたことで、「一気にいろいろな殻が破れた気がした」と語る為末さん。
リズムの違いが走りの違い? スポーツにも文化をみる
海外での日々は、アスリートとしても、本当に学ぶことが多い一年でした。どんなにすごいオリンピック選手やメダリストも、しばらく生活を共にすると、弱点もあれば苦手もある同じ人間だと思えるようになります。おかげで相手がスター選手でも、良い意味で肩の力を抜いて、付き合えるようになっていきました。
海外での競技生活では、急に開始時間が変更になるといった、日本では考えられないことが、当たり前のように起きましたが、まがりなりにも試合をこなしていくうち、自分は意外とこういう局面に弱いとか、引っ込み思案なところがあるとか、日本にいた時には気付かなかった、思いがけない自己発見もしました。
一例として、私は日本では平均的な身長ですが、世界一背が高いオランダ人の間に入ると、たちまち背が低い人になってしまいます。周りがどういう人たちかによって、自分の立ち位置が変わるのです。面白いもので、こうして相対的に見る視点を得たことで、より深く自分を知ることができるようになったと思います。
ところで、陸上競技はやはりアフリカ系の選手が強く、陸上チームでは、ほぼ全員がアフリカ系ということも、珍しくありません。そんなチームメイトたちと、ダンスパーティーに出かけた時のことです。フロアでは大勢の人が、思い思いに踊っていて、みんなの頭が、ビートを刻むように上下しています。そのうち私は妙なことに気付きました。私が伸び上がっている時、他の人たちは反対に、身体を沈めているのです。原因はすぐ分かりました。彼らはまさに音楽でいう「裏拍」で踊っていて、私だけリズムの取り方がみんなと逆だったのです。
そういえば、思い当たることはありました。一緒に練習しながら、チームメイトたちと自分の走りは、何かが決定的に違うと、ずっと気に掛かっていたのです。もしかすると、トレーニングで鍛えるといったこととはまったく別に、持って生まれたリズム感の違いのような、文化的要因があるのかもしれないと、この一件でひらめきました。何気ない出来事でしたが、今まで考えてもみなかった切り口で、自分の走りを見直すきっかけになりました。
身体を通じて人間の可能性を拓く仕事
もう一つのターニングポイントは、引退して仕事を始めた時です。実業の世界に進んだのは、最初は未知の分野への好奇心からです。友人たちが話す企業の言語、仕事の言語を理解したかったし、新しい視点を得たいという期待もありました。
2018年には、スポーツテクノロジー関連のプロジェクトを行う会社を立ち上げて、人を雇い、組織を運営するようになりました。現役時代はずっと個人競技でやってきたので、人を巻き込んで事業を進めるというのは、勝手が違って最初は大変でしたが、やりがいも感じました。
この会社では今、委託を受けて屋内ランニング施設の運営を行っています。「すべての人に動く喜びを」というコンセプトで、私たちも設計段階から関わりました。かつて陸上競技場といえば、健常な競技者のための施設でしたが、この施設には段差が一つもなく、地域の子どもたちやお年寄りから、国内の選手、海外の選手、オリンピアンにパラリンピアンと、誰でも使えるように作られていています。
ここには義足の会社も入っていて、パラリンピアンに競技用義足を提供したり、子ども用の義足を貸し出したりしているのです。義足の選手が普段用の義足を外し、競技用の義足を付けるところを見た子どもたちは、初めこそギョッとしていますが、二度、三度と目にするうちに、意識すらしなくなっていきます。偏見というのは、慣れの問題なのです。
現役時代、私は競技者としての成功をひたすら追い求め、練習に没頭していました。しかし多くの人と一緒に、社会で仕事をするようになると、企業としての「志」が重要になってきます。私たちは誰のために存在するのか、我が社は何のために存在するのか、という問いに、仕事の文脈でどう答えるべきか。それを考えるのにとても時間がかかりました。今思うのは、「人は身体を通じて、もっと可能性を拓けるはずだ」ということです。私の背景はスポーツですから、スポーツで可能性を拓く機会を多くの人に提供し、世の中を変えていきたい。それが私たちの「志」です。
記事の感想やご意見をお送りください
抽選で毎月3名様にAmazonギフトカード1000円分をプレゼントします
キャンペーン主催:(一財)国際ビジネスコミュニケーション協会
AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
- 1
- 2