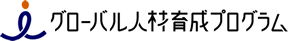Leader's Voice


「変わろうとしない自分」と戦い続けるプロセスが成長するということ
プロフィール
高野 登(たかの・のぼる)
1953年長野県生まれ。プリンスホテルスクール卒業後、アメリカに渡り、ザ・キタノ・ニューヨーク、スタットラー・ヒルトン、ニューヨーク・プラザホテルなどでホテルマンとして活躍。1990年、リッツ・カールトンの創業メンバーとともにザ・リッツ・カールトン・サンフランシスコ開業に尽力。1994年に日本支社長として帰国。1997年に大阪、2007年に東京の開業をサポート。日本にリッツ・カールトンブランドを根づかせた。2010年、人とホスピタリティ研究所を設立。リーダーシップや人財育成などをテーマに研修や講演活動を行っている。
- 目次
- 個としての軸
- 多様性活用力
引っ込み思案の青年が渡米の夢を抱くまで

地元長野で塾長を務める長野寺子屋百年塾「新春談話会 in 善光寺」にて。
私がプリンスホテルスクールに入学したのは、「偶然」と言っていいかもしれません。
小さいころから引っ込み思案で、人前に出るのが苦手。家にお客さんが来ると、押入れに隠れてしまうような子どもでした。だから、将来は人前に出なくてもいい仕事に就きたいと考えていたのです。簿記の資格を持っていれば、ずっと人に会わずに帳簿の仕事ができるのではないかと考えて、商業高校に進学しました。でも、実際にはそんな仕事なんてないですよね。
高校3年生のある日、受験雑誌をパラパラと眺めていると、1枚のハガキがついているのを見つけました。「赤坂に日本初のホテルマン養成スクールが開校」という学校案内のハガキです。それ以来、その雑誌を開くたびにハガキのところで手が止まる。気になって仕方がなくて資料請求をしたのです。
届いた資料には、海外のホテルの写真がたくさん載っていました。そこで働くホテルマンの様子を見て、なぜか、自分が一緒に働いている姿が見えたのです。その不思議な感覚が頭から離れず、1次試験の申込書を送りました。1次試験に合格し、次は面接という段階で先生や両親にうち明けると、内気な性格には向いていないと大反対。でも、「これだ!」とスイッチが入ると、頑固な性格なんです。反対を押し切ってホテルスクールに入学することになりました。
私と同じ年に入学した一期生の顔ぶれは、非常にユニークな面々でした。わずか2年の間でしたが、彼らとともに学ぶうちに、内向的な自分を守っていた鎧のようなものが、ぽろぽろ落ちていくような感覚がありました。
何といっても忘れがたいのは、アメリカへの修学旅行です。バンクーバーから入ってロサンゼルスまでバスで行ったのですが、当時はまだ開発も進んでいなくて、走っても走っても畑ばかり。その車窓から、セスナ機が農薬を散布している様子が目に入りました。農薬といえば、私の地元の長野では、背中に噴霧器を背負ってカシャカシャと手動でまくもの。この国はセスナ機で農薬をまくのかと興奮した瞬間に、「この国で働いてみたい!この国のスケールの大きさを感じてみたい!」とスイッチが入り、アメリカに行くとすでに決めていました。
忘れられないバーテンダーとの出会い

ニューヨーク・プラザホテルでは国際営業部に所属し、日本を含むアジア・太平洋地区への営業活動をしていた高野さん。
卒業が近づき、ほとんどの学生は就職先が決まっていくなか、私はアメリカのホテルで働く意思を曲げなかったので、就職先がなかなか見つかりませんでした。そんなとき、長野の北野建設がニューヨークにホテルを開業するので、元気のいいホテルマンを探している、という話が飛び込んできたのです。北野建設の社長が私と同じ高校の出身だったこともあり、すぐにお会いする機会を得ました。社長は野球部出身で、「昔は野球が強かったのに」「後輩がだらしなくてすみません」といった話をして、「じゃあ書類を書いておいて」と言われて……。それが、入社手続き用の書類だったのです。高校の後輩という縁で特別に入社できたことは後で知りました。
それから8カ月後にアメリカにわたり、ザ・キタノ・ニューヨークで私のホテルマン人生がスタートしました。渡米に向けての英語学習は特にしなかったので、最初は英語に苦労したものです。ホテルの近くにバーがあり、仕事に疲れては、そこに足を運ぶようになりました。実は、そのバーこそが、私の英語を磨いてくれる大切な場所になったのです。
通ううちに、ボブというバーテンダーが話しかけてくれるようになりました。初めはテーブル席に座っていましたが、そのうちに前に座るように言われ、カウンターの端からだんだん真ん中の席に。顔馴染みとなり居合わせるお客さんとも自然に話すようになりました。こういうのが、教科書で学ぶような「会話」ではなく、生きた「対話」なんだと実感しました。対話というのは、その場の空気、相手の表情や気持ちを五感で感じとり、互いを分かり合おうという心のやりとりなんです。バーにはいろいろな人がいました。「第二次世界対戦で大親友が日本人に殺された」という人も。日本にいたら考える機会などなかったであろうこともたくさん考えました。生身の人間を相手に「対話」する体験というのは、人を成長させるものだと思います。
のちのち知ったのですが、ボブは銀行の元役員で、余生はバーテンをしながら仲間達と話をして過ごしたいと、この仕事を始めたそうです。日本人の若者が何か一生懸命やっているのを見て、応援してやろうという気持ちが生まれたのかもしれません。ボブやバーのお客さんとの出会いがなければ、私の英語習得はもっと時間がかかっていたことでしょう。
記事の感想やご意見をお送りください
抽選で毎月3名様にAmazonギフトカード1000円分をプレゼントします
キャンペーン主催:(一財)国際ビジネスコミュニケーション協会
AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
- 1
- 2