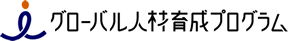Leader's Voice


就労支援で難民の日本での活躍に新たな道を切り拓く
プロフィール
渡部カンコロンゴ清花(わたなべかんころんご・さやか)
1991年生まれ。静岡県浜松市出身。様々な背景を持つ子どもや若者が出入りする実家で育つ。大学時代はバングラデシュの紛争地にてNGO駐在員・国連開発計画(UNDP)のインターンとして平和構築プロジェクトに参画。2016年、日本に逃れてきた難民の仲間たちとNPO法人WELgeeを設立。グローバル・コンソーシアムINCO主催「Woman Entrepreneur of the Year Award 2018」グランプリ。「Forbes 30 under 30」Japan / Asia選出。東京大学大学院総合文化研究科・人間の安全保障プログラム修士課程修了。
課題山積の難民問題を前に、ドミノ倒しの1つ目を探す日々
私がWELgeeの活動を始めたのは大学院生だった2016年です。それから7年間で300人以上の難民に伴走し、そのうち22人の日本企業での就労を実現しましたが、2025年までに100のキャリアを活かした就労事例を作ることを当面の目標にしています。良い事例がまず100できれば、波及効果が期待できる。そうすれば、1つのNPOの力ではなく、経済界や社会のムーブメントとなって自動的に動き出します。私たちが手を離しても車輪が転がっていく地点まで、自転車を押しながら坂道を上っているイメージですね。LGBTQも子どもの貧困も、今でこそ社会問題として国会でも頻繁に議題に上がるようになりましたが、それは、注目されていない時期に坂道を上ることを諦めない人たちがいたからだと思うのです。
ここまでの歩みは模索の連続です。特に最初の数年は、大きすぎる課題に面食らい、まさにドミノ倒しの最初の1個を探している感覚でした。最近はウクライナ情勢を受けて日本でも難民問題への注目度が上がっていますが、アフガニスタンやミャンマー、アフリカ諸国などから、保証人もいないまま単身で日本に避難してきた人たちは以前からたくさんいて、今以上に足りないものだらけ。「言葉がわからない」「住む場所がない」「食べるものがない」「難民申請の仕方がわからない」。難民の背景を持つ若者たちに困っていることを聞けば、芋づる式にいくらでも出てきます。当初は一つひとつ対応していましたが、ドミノが倒れていく気がしない。レバレッジポイントを探しながら、シェアハウス事業を始めるなど、とにかく手探りでしたね。
「ここには爆弾は落ちてこない。でも生きている気がしない」。手探りの中でハッとさせられた言葉の1つが、パレスチナのガザから来ていた元看護師の男性のこの言葉でした。命に関わる仕事がしたくて看護師になり、病院に運ばれてくる子どもたちの手当てをしていたという彼が、病院も無差別に攻撃を受ける祖国の現実に望みを失い、やっとの思いで辿り着いたのが日本。難民認定を待つ間、清掃や解体の仕事に就いていましたが、どんな仕事も尊いという想いは抱きながらも、この状況が何年も続くことに絶望していたのです。日本の難民認定率は1%未満と、他の先進国に比べて抜きん出て低いのが現状です。何年も待ったところで、日本にいられる資格を得られるのは100人に1人もいない。待った挙句、不認定の結果が出れば、その先にあるのは祖国への強制送還です。やりたいことが見つかって活動を始めていた大学院生の私と、人の命を救う仕事を切望しながらすべての道を閉ざされている同年代の彼。「働くことは生きること」という彼の言葉に、もしかしたらキャリアや仕事が突破口になるのではないかと気づいたのが、現在の活動のきっかけでした。
子どもの頃から思っていた「本当かな」
ただ、いざ動き出してみると、自分が日本の難民制度について何も知らないことを思い知ります。日本に辿り着いた人たちは、祖国にも日本にも法的地位も居場所もありません。地球上のどこにも足場がなく、いわば存在することを認められていない状態です。日本に生きる外国人にとって在留資格は命綱。まずは自分たちが難民制度のプロフェッショナルにならないと解決策なんて無責任に考えられない。そう考え、入管行政を専門とする士業の人たちの集まりに参加しました。恥ずかしいことに、話の内容の8割はわかりませんでしたが、とても大事なことだということはわかった。その後の懇親会で、名刺もないのに「難民の問題をどうにか解決したいと考えている大学院生です」と名乗って、行政書士に教えを乞いました。その後、顧問行政書士になっていただき、長年活動を支えていただいています。

外にも世界が広がっていることを知り、現状にとらわれない視点を持てたと語る渡部さん。
もともと行動力はあるかもしれません。大学時代、バングラデシュの先住民族が迫害を受けていることを知ったときも、外国人の滞在許可を得るために内務省と6カ月間交渉しました。こうした行動の裏にあるのはとにかく自分の目で見たいという想い。これは変わらない私の性質なのだと思います。難民問題についても、例えば日本の難民認定率の低さと変わらない現状は調べてわかった。でも「本当に不可能なのだろうか」と疑問を持ち、「他国のように、難民認定以外の方法もあるのではないか」と考えてしまう。WELgeeのキャリア伴走で企業に就職した22人のうち、難民認定を待つ間の「特定活動」という不安定な資格から、専門的・技術的分野の安定的な在留資格への変更を実現した事例は7例(2023年3月現在)に上りますが、当初、資格の変更は無理だと言われていました。でも法律や運用を読み込んでいくと、「できる」とは書いていないけれど、「できない」とも書いていない。弁護士に聞いてもわからない。だから挑戦してみたのです。
振り返ると、子どもの頃から、先生やどこかの偉い人が言ったことを「本当かな」と思っていたような気がします。もしかしたら、きっかけは7歳の時、助産師をしている叔母を訪ねてバングラデシュで2週間ほど滞在したことだったかもしれません。私が育ったのは静岡県の田舎の町。通っていた小学校も学校全体で100人くらいだし、町自体、同質性が高い。外国人もいない、東京からも離れた田舎にいながら、「この空間だけじゃない」という思いを常に抱いていたのは、外に別の世界があることを知っていたからなのかもしれませんね。子どもの頃は自分の足で外に出られないことにもどかしさも感じていたのでしょう。
記事の感想やご意見をお送りください
抽選で毎月3名様にAmazonギフトカード1000円分をプレゼントします
キャンペーン主催:(一財)国際ビジネスコミュニケーション協会
AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
- 1
- 2